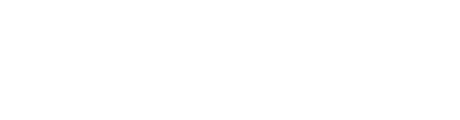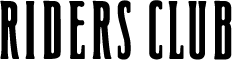青木兄弟による最高峰クラス同時表彰台の特別なレース『イモラの軌跡』を振り返る

80年代から世界グランプリを撮影し続けた折原弘之がパドックで見て、聞いて、感じたインサイドストーリーをご紹介。今回は、日本が誇る世界GPレーサーブラザーズ、青木兄弟が実現した、最高峰クラス同時表彰台の日。
イモラの奇跡 フォトグラファー折原弘之が振り返るパドックから見たコンチネンタルサーカス

’71年群馬県生まれ。青木三兄弟の長兄。’89年に史上最年少で国際A級に昇格。’93年から世界GP250クラスに参戦。’97年からGP500クラスに昇格し、いきなりランキング3位を獲得。’98年にスズキへ移籍。世界GP引退後も鈴鹿8耐などで優勝。50歳を迎える今年も鈴鹿8耐参戦を表明しているほか、本誌ライテク企画、ライディングパーティなどでも活躍
青木拓磨(写真右)
’74年群馬県生まれ。’95年にホンダワークスで全日本王座に輝く。ワイルドカードで世界GP日本ラウンドを走り、3位表彰台を獲得。’97年から世界GP500クラスに、レプソル・ホンダからフル参戦。テスト中の事故により引退した後も、四輪レーサー、バイク教室の運営、障がい者ライダーを支援する「サイドスタンドプロジェクト」を設立するなど、精力的に活動する
「兄貴、コース走りに行こうぜ」 いつも通り木曜日のパドックを、青木宣篤選手のモーターホームで過ごしていると青木拓磨選手が迎えに来た。’97年から世界GPライダーとして、ヨーロッパに乗り込んだタクマはコースを覚えるのに、兄のノブをランニングに誘う。
「折さんも行こうよ、スクーター貸すから」と、僕もランニングに付き合わされる。この会話はルーティンになりかけていて、だいぶ慣れてきた。アップダウンのきついイモラのコースを走るには、一人より二人、二人より三人の方が楽しい。
二人は時折コースについて話しながら、全長約5㎞のコースを黙々と走っている。僕はといえばタクマに借りたスクーターで、撮影の下見を兼ねてのんびりと並走していた。いつも通りのGPウイークの木曜を過ごしていたのだが、その週末、この二人に素晴らしい奇跡を見せてもらえるとは夢にも思ってもいなかった。
世界GP参戦1年目のタクマはこう言った。
「初めてのサーキットっていうのは、大した問題じゃないんだ。もちろん知ってるサーキットに比べれば、攻めきれないかも知れないけど。なんとかなるんだよ。
ただマシンがさ、3速くらいまでウイリーが止まらないのよ。やれる事はやってるんだけど、どうしてもフロントが浮いて来ちゃって。立ち上がりでアクセル戻したりしてるんだよね」と、2気筒のNSR500Vの難しさに悩んでいた。
一方ノブはといえば、後に自身が乗った中で最高のマシンと評したNSR500に乗り、「なんか調子いい。勝てそうな気がするくらい調子いい」と、今シーズンのマシンの仕上がりにご満悦な様子。そんな二人の予選結果は、コメントの通りノブがフロントローを獲得、タクマは3列目に沈んでいた。
金曜日のフリー走行、土曜日の予選を終え、夜は岡田忠之選手と夕食を共にした。そこでタクマの乗る500Vについて聞いてみた。
「タクマは、良くやってると思うよ。あのバイクは、難しいんだよ。トルクが太いからアクセル開ければフロントが浮いてくるし、車体が軽いせいか200㎞/hくらいから開けてもホイールスピンするんだよ。厄介なバイクなんだよね」と、自身が苦しんだ経験を話してくれた。GPライダーをもってしても、走らせるのが難しいマシンなのだ。
対するノブの500について。「去年型のノブのマシンは、バランスが良いんだよ。ピーキーなエンジンだし、今年のマシンの方がパワーも出てるけど、扱いやすいんだよ。コースによっては今年のマシンより、走る可能性はあると思うよ」と、やはり絶賛していた。
二人の印象と岡田選手の話が一致していたので、ノブの表彰台はあるけどタクマの表彰台は遠いな。などと思いながら夕食を済ませホテルに帰った。

晴天のイモラで始まったレースは、嬉しい誤算の連続だった。フロントローからスタートしたノブは、王者ミック・ドゥーハンを終始追い回し2位をキープ。3列目スタートのタクマも暴れるマシンをなだめすかし、グイグイ順位を上げてきた。
もしかしたら“ノブが優勝、タクマが表彰台もあるかも”などと思いながら、ワクワクした気持ちでレースを撮影していた。だがそんなに話は上手くいかない。終盤ノブはミックに離され始め、単独の2位を走ることになる。
タクマはといえば、どんどん順位を上げ3位まで上がってきた。ノブの優勝はなかったが、兄弟での表彰台は見えてきた。ノブやタクマが高校生の頃から撮っている僕は、叫びだしたくなるくらい感情を揺さぶられた。
あの二人が世界GPの最高峰クラスで、揃ってポディウムに上る。考えただけで涙が出てきそうだ。最終ラップを迎える頃には、もう居ても立っても居られない気分だ。とにかく無事にチェッカーを受けてくれ。祈るような気持ちで撮影していた。

二人が無事にチェッカーを受けた時には、膝から崩れ落ちそうなくらいの喜びが湧いてきた。チームの人間でも身内でもないのに、これほど喜べるものなのか。とにかく一刻も早く“おめでとう”を言いたい。そう思い、パルクフェルメに走ったが、まずはチームと共に喜んでもらわないと……と思い一歩引いていると、チームに挨拶を終えたノブと目が合った。
「スゲェー、兄弟で表彰か」そう言うとノブがキョトンとした顔をした。そう、彼は自分の順位で一杯一杯で、タクマの表彰台を知らなかったのだ。「えっ、タクマ3位なの?」
そう言ったそばから、タクマが現れ二人は抱き合いながら喜びを分かち合っていた。その光景は、青木兄弟を中心に歓喜の輪がパドック中に広まっていったようにさえ思えた。青木兄弟がイモラで見せてくれた奇跡、最高峰クラスでの兄弟表彰台。この記録は、いまだに青木兄弟しか達成していない。
その場にいる事が許され、同じ空間を共有できた事は最高の瞬間の一つだ。そしてその晩は言うまでもなく、パドックでドンチャン騒ぎが夜半まで続いた。
月曜日の朝はこれまで見たこともないくらい顔がムクミ、昼過ぎまで酒臭さが抜けなかった。それでも次のレースへ向けて、ノソノソと荷造りを始めた。レースの後は、一人で移動するため孤独感が強いのだが、この日ばかりは楽しい気分で移動した。
次の木曜日に訪れるいつもの非日常が楽しみでならなかった。


折原弘之
1963年生まれ。’83年に渡米して海外での撮影を開始。以来国内外のレースを撮影。MotoGPやF1、スーパーGTなど幅広い現場で活躍する