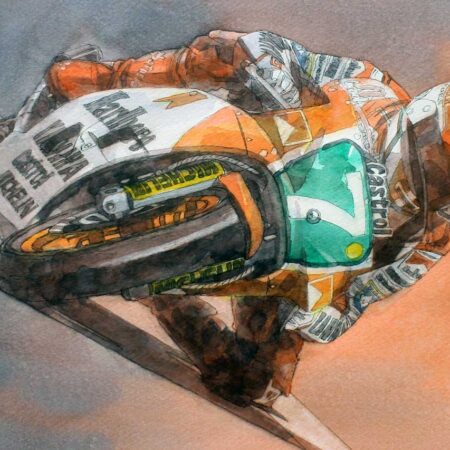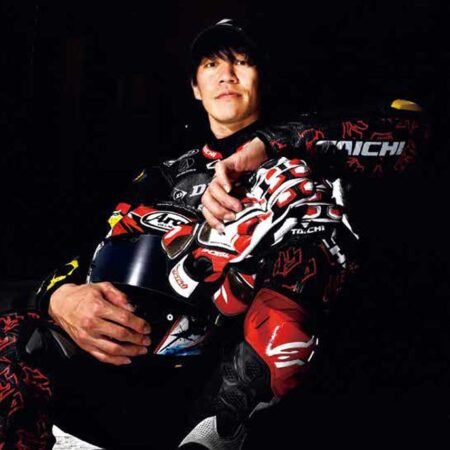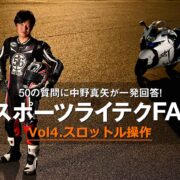タイヤメーカーが語る鈴鹿8耐の戦い方とは? 【BRIDGESTONE×SUZUKA 8hours】

今年も『真夏の祭典』がやってきた 真夏の祭典とも呼ばれる、鈴鹿8時間耐久ロードレース。過酷なほど暑い7月の最終週に多数のバイク好き・レース好きが鈴鹿サーキットに集結して、8時間に及ぶ長い戦いを楽しむ。2018年は7月29日(日)が決勝だった。 車両メーカーにとっては、威信を懸けた本気の戦いだ。
PHOTO/SUZUKA CIRCUIT、TSR、RIDERS CLUB
取材協力/BRIDGESTONE
世界耐久レースのなかで鈴鹿8耐が特別な理由
特に日本メーカーにとって、日本最大の二輪レースで勝つことは、特別な意味がある。鈴鹿8耐での優勝は、世界に轟くのだ。そして中団以降のチームにも、それぞれの目標がある。完走すること。前回より多くの周回数をこなすこと。あるいは、レースを楽しむこと……。
ブリヂストンには、大きな目標があった。’06年から続いている勝利をもぎ獲り、13連覇を成し遂げることだ。だが、その実現は容易ではない。鈴鹿8耐は、その内容においても特別なのだ。
「耐久レース」と銘打たれながらも、スタートからゴールまでの8時間、延々とハイペースが続く。真夏の午前11時半から午後7時半まで、路面温度が極めて高い鈴鹿サーキットを走り続ける。世界的に見ても唯一無二の『スプリント耐久レース』である。
ブリヂストンのレースタイヤ開発を担うエンジニアの松永真利さんは、「鈴鹿8耐はEWC(世界耐久レース)シリーズの最終戦という位置づけですが、レースの特性はかなり特殊です」と言う。
EWCの戦いは、複雑かつ戦略的だ。燃費に余裕があるから、例えば「スタート時には燃料を満タンにせず、序盤にいいポジションを確保する」といった作戦を立てられる。
ル・マン24時間レースなどでは、タイヤも2、3種類を使う。戦いが、凍えるほど寒い夜から路面温度が45度にもなる日中へと移り変わる時、どのタイミングでどの種類のタイヤに交換するかがポイントになる。

「転倒などでペースカーが入った時なども、給油のタイミングをどうするかなど、臨機応変にその場その場でプランを組み立て直していく必要があります。チーム監督の采配次第で、レース結果が大きく変わるのがEWCなんです」と松永さ一方の鈴鹿8耐は、もっとシンプルだ。
「午前11時半から午後7時半まで、気温も路面温度もずっと高いのが鈴鹿8耐ですからね(笑)。使うタイヤも基本的には1種類です。7回ピットインして8スティント、というのが今の8耐で勝つための定石。燃費もキッチリと1スティント保つように計算されています。すべてを予定通りこなしたチームが勝つという、言わば力業ですね」
EWCで求められるタイヤ性能は、フレキシブルであることだ。より幅広い温度変化に対応する扱いやすさが必要となる。また、路面グリップが低いサーキットを舞台に行われることも多く、グリップを失ったとしても急激に滑っていくことのないような、マイルドな特性が好まれる。
鈴鹿8耐のタイヤに求められるのは、ハイグリップかつ安定した性能
鈴鹿8耐は、もう少し違ったピンポイントの性能が求められる。EWCに比べればハイグリップであることと、極度に高い安定性だ。 毎年、ほぼ同じコンディションで行われるのが鈴鹿8耐である。
雨が降るなどの不確定要素はあるが、ほぼだいたい同じ気温、同じぐらいのペースの戦いが、高い路面グリップのサーキットで展開している。十分に揃っている過去のデータに基づいて、プログラムを組むのがセオリーだ。だからタイヤも、予想しやすい安定性能が必要とされる。 さらに、電子制御……トラクションコントロールシステムも、タイヤに安定性を求める。
トラコンは、不確定要素を嫌うのだ。 例えばタイヤのグリップがスティントの序盤と終盤で大きく変わるようだと、トラコンは利きすぎたり利かなすぎたりする。摩耗による周長の変化にも敏感だ。
「ピークグリップの高さより、フラットにパフォーマンスを発揮し続けるタイヤが、鈴鹿8耐で勝つためには必要です」と松永さん。
「ピークグリップが上がるということは、実はリスクにもなり得るんです。つまり、そのグリップが下がった時にはどうするんだ、と」 いわゆる「1発タイムが出るタイヤ」よりも、コンスタントにハイペースを保てるタイヤの方がよい、という考え方だ。

「かつて電子制御が今ほどなかった時代には、どんな特性のタイヤをつくり込むかによって、勝敗を分けるということがありました。例えば硬くて保ちがいいタイヤにするとか、タレないタイヤにするといったつくり込みの方向性が、勝負に影響していたんです。
でも今は、電子制御の足を引っ張らないタイヤ作りが重要です。グリップのレベルもタイヤ周長もなるべく経時変化せず、要するに『何も変わらないタイヤ』を目指すんです」と松永さん。
ゴムの質ではなく、構造と形状で安定した性能を作る
安定した特性を持つタイヤの実現のためには、地道な技術的なトライが必要だ。コンパウンド(ゴム)でグリップを稼ぐようなシンプルな方法では成し遂げられない。構造と形状を徹底的に見直しながら、「変化の少ない安定したタイヤ」がつくり込まれていった。
ここまでの12連覇は、その賜物だった。ハイペースを前提として、長年をかけて緻密に組み上げられたこのレースは、文字通り、わずかなミスも許されない。コース上にあふれるバックマーカー(周回遅れ)を交わしながらもペースを乱さず、予定通りの走りを淡々と、しかも高次元で繰り返すこと。

これが唯一、頂点へと続く道である。「真夏の熱いバトル」と表現されることもある鈴鹿8耐だが、少なくともチームは、ライダーは、熱くなっていてはいけない。もちろん、タイヤメーカーであるブリヂストンも。 松永さんは、「勝つことは、我々ブリヂストンにとって最大の目標です」と言いながらも、別の観点も持っている。
「僕個人としては、各チームに安定したタイヤを供給し、それぞれが望む形のレースができるようにサポートしたい」 自身も過去にレースをしていたことがあり、レースを心から愛する松永さんならではの言葉だ。今年の鈴鹿8耐で、ブリヂストンは31チームにタイヤを供給する。
そのすべてが、「よいレースを戦い抜くこと」。それが松永さんの望みなのだ。
ヤマハ、スズキ、カワサキの3社が求めるタイヤと、ホンダの求めるタイヤは違う
タイヤ開発エンジニアの目からすると、ヤマハ、スズキ、そしてカワサキがタイヤに求める要件は似た傾向にあり、ホンダだけが異なるのだという。
「ヤマハ、スズキ、カワサキの3メーカーは、よりしなやかなリヤタイヤを望みます。一方のホンダは、しっかりしたリヤタイヤを求めるんです。これらのタイヤは基本的にどのチームもテストしているので、例えばホンダがヤマハのようなリヤタイヤを求めれば、提供することは可能です。ところが面白いもので、みんなそうはしない(笑)。やはりそれぞれの考え方があって、電子制御のつくり込み方も異なる。自分たちに合うタイヤというものがあるんです。我々の仕事でもっとも重要なのは、各チームと話し合うなかでチームがどんなレースを望んでいるかを詳細にヒアリングし、最適なタイヤを提供することを重視しているんです」
タイヤメーカーとして、自社の連覇をさらに積み重ねたいという思いはもちろん持っている。でもそれ以上に松永さんは、各チームの希望を叶えることを第1に考えているのだ。
3連覇のヤマハを見舞ったタイヤサイズ変更
昨年、ヤマハ・ファクトリー・レーシングは使い慣れた16・5インチタイヤで3連覇したが、今年は全車が17インチタイヤで戦わなくてはならない。成熟したパッケージに0.5インチの変化は大きい。
しかしブリヂストンは着実にタイヤ開発を進め、結果、同ヤマハの中須賀選手は今年、16.5インチで出したコースレコードを見事17インチで塗り替えた。タイヤ開発だけでなく、チーム、マシン、ライダーとのマッチングまで成熟しているといえるだろう。

「自分たちは裏方だと思っていますよ」と松永さんは笑う。ブリヂストンのあまりの強さ、あまりの圧勝が続く今の鈴鹿8耐で、確かにタイヤに注目が集まることはほとんどない。
しかし一方で松永さんは、「接地しているのはタイヤだけですからね」とプライドを覗かせもするのだ。
トラコンにマッチした特性のタイヤ
先の電子制御との兼ね合いでいえば、「トラコンを利かせすぎないようにするタイヤ」を開発したところ、タイムが大幅に向上した、などという実績も持っている。 トラコンは多かれ少なかれ、エンジンパワーをカットする制御である。
できるだけトラコンを利かせない方が――つまりほどよいスピンレートを備えているタイヤの方がタイムアップさせられる。さらにトラコンが利くとライダーはスロットルを全開にしがちなので、燃費の面でも不利になるのだ。
極端にフラットなパフォーマンスが求められる、鈴鹿8耐で勝てるタイヤ。ピークグリップという分かりやすい指標よりも、コンスタントさという地味とも思える特性が必要だ。そして自らを「裏方だ」と言い切る姿勢。すべてが控えめとも言える。

だがやはり、勝負の鍵を握っているのは、タイヤなのだ。勝てるタイヤなくして、鈴鹿8耐の勝利はない。 全日本ロード・JSB1000クラスを主な開発の舞台として、1年をかけて地道な進歩を続けるブリヂストンタイヤ。メーカー、チーム、ライダーの目標を達成させるべく、確実に歩みを進めている。7月29日、午後7時半すぎ。鈴鹿サーキットには戦いを終えた各チームの健闘を称える花火が打ち上がった。
表彰台の頂点に立ったライダーたちは、誇らしげに「BRIDGESTONE」のロゴが映える赤いウイナーズキャップに手を添える。美しい花火と赤いキャップが、歓喜に湧く鈴鹿サーキットを彩る。「真夏の祭典」にふさわしい華々しさとともに。