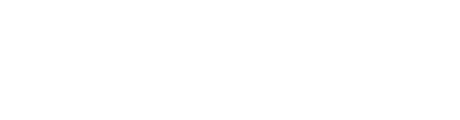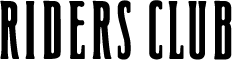『プレイバック・インプレ』-GSXの系譜-生まれ変わったSUZUKI KATANA
生まれ変わった「KATANA」がついに日本のストリートを走り始めた 過去に軸足を置いたネオクラシックというよりも未来を見据えたブランニューモデルが見せるフィーリングをお届けしよう ライダースクラブも含め、すでにさまざまな紙媒体、そしてさまざまなウェブメディアで新型カタナの話題が取り上げられている。 ゆえに「ケルンの衝撃」や「ハンス・ムート」をキーワードにして始まる初代カタナの誕生物語にも、新型にまつわる「エンジンズエンジニア」や「ロドルフォ・フラスコーニ」のエピソードにもそろそろ食傷気味になっている頃かもしれない。 というわけで、今回は実際にストリートで乗ってみてどうだったのか?」という点に軸足を置いて紹介していこう。 編集部に到着したカタナは、オドメーターに100kmほどの距離が刻まれていたに過ぎない、降ろしたての新車だった。 パーツの加工精度や組付技術は、ひと昔前と異なって飛躍的に向上しているものの、エンジンやミッション、サスペンションの摺動部は、今もある程度距離を重ねた方がスムーズに動くのは歴然とした事実だ。実際、今回のテスト車両もメーターの数値が進むにつれて刻々とコンディションが変化。もちろんポジティブな方向へ、である。  カワサキからZ900RSが発表された時と同様、カタナのスタイリングに関しては少なからずヒステリックな声が聞こえてくる。 オリジナルが持っていた伸びやかなルックスとは印象が異なること、そしてハンドルがクリップオンではなく、ワンピースのバータイプになったことへの失望の声がそれだが、特にこれからオーナーになろうかというユーザーの皆さんは、まったくとらわれる必要がない。 実車を目の前にし、そのシートにまたがってみれば、スポーツバイクとしての及第点を大きく超え、しっくりとくる感覚は近年のモデルの中でも随一のものと分かったからだ。 それでいて、外観の印象はやはりカタナである。確かに、構成パーツのひとつひとつを見れば、オリジナルと新型との間にはなにひとつ共通項がないのだが、そのたたずまいはカタナそのもの。これは単に昔に寄せたネオクラシックではなく、未来へ向けて正常進化させた新たなカタチとして見るべきである。 広く知られているように、ベースになっているのは15年に登場したスポーツネイキッドであるGSX‐S1000だ。主要な構成パーツを流用しつつ、シートレールは刷新。それがカタナらしさのひとつであり、デザイン上のアクセントにもなっているツートーンのシートを内部から支えている。
カワサキからZ900RSが発表された時と同様、カタナのスタイリングに関しては少なからずヒステリックな声が聞こえてくる。 オリジナルが持っていた伸びやかなルックスとは印象が異なること、そしてハンドルがクリップオンではなく、ワンピースのバータイプになったことへの失望の声がそれだが、特にこれからオーナーになろうかというユーザーの皆さんは、まったくとらわれる必要がない。 実車を目の前にし、そのシートにまたがってみれば、スポーツバイクとしての及第点を大きく超え、しっくりとくる感覚は近年のモデルの中でも随一のものと分かったからだ。 それでいて、外観の印象はやはりカタナである。確かに、構成パーツのひとつひとつを見れば、オリジナルと新型との間にはなにひとつ共通項がないのだが、そのたたずまいはカタナそのもの。これは単に昔に寄せたネオクラシックではなく、未来へ向けて正常進化させた新たなカタチとして見るべきである。 広く知られているように、ベースになっているのは15年に登場したスポーツネイキッドであるGSX‐S1000だ。主要な構成パーツを流用しつつ、シートレールは刷新。それがカタナらしさのひとつであり、デザイン上のアクセントにもなっているツートーンのシートを内部から支えている。 

ワインディングに木霊するマルチシリンダーならではの咆哮
シート高は825㎜。GSX‐Sのそれより15㎜高く、またがるとその数値が示す通り少し腰高だ。身長174㎝のライダー(伊丹)が乗った状態で地面にカカトは接地せず、30~40㎜程度浮いている。 ただし、極低速走行時にも不安はなく、Uターンを強いられるような場面での一体感はGSX‐Sよりも高く、扱いやすさが光る。 その理由は、ライダーの乗車位置がかなり前方へ移動したからだ。相対的にハンドルとシートの距離が縮まり、ライディングポジションのコンパクト化を実現。そのハンドルもグリップ部分がGSX‐S比でわずかに引かれるなど、ライダーそのものが車体を構成するパーツの一部としてマスの集中化に貢献している。そんな印象を強く受けた。 シート表皮とステップバーのグリップ力、そして燃料タンクのホールド性はスズキ車の伝統に倣ったものであり、つまり良好だ。 下半身を安定させたい時はしっかりと支えることができる密着性があり、前後左右に動きたい時はタイムラグなくそれを行える自由度を確保。パワフルなビッグバイクを操っているという緊張感は少なく、まるで長年乗っている愛車のようにスッと体に馴染んでくる。 また、ごく自然に手を伸ばした位置にグリップがあり、絞りや幅もそれに従ったものになっている。ハンドルに関しては、開発過程で15パターンのサイズと形状が試されたとのことだが、それが効果を発揮し、軽く添えるようにリラックスして乗ることも、ストリートファイターのように体重を預けることも許容する高い自由度がそこにもあった。 
リニア、ナチュラル、フレキシブル……扱いやすさのすべてがそこにある
オリジナルファンの間で物議をかもしたアップライトな見た目だが、ハンドルをフルに切った時の状態を見れば、可能な限りクリアランスが詰められていることが分かる。スポーツ性、実用性、安全性の狭間の中で導き出された最適解と言っていい。 これ以上低く、あるいは狭くしようとすれば、ハンドル切れ角を極端に制限するか、燃料タンクとエアボックスどちらかの容量を犠牲にするしかない。 燃料タンクは、現状でも12L(GSX‐Sは17L)だ。そのスタイルのため、すでに少なくない代償を払っていることを思えば納得できるはずだ。 WMTCモードの計算燃費値は、19.1㎞/Lを公称し、計算上の航続距離は230㎞弱となる。現実的には多くのライダーがツーリングにも使うわけで、利便性を踏まえるとギリギリの落としどころだろう。 発進や低速走行時にエンジン回転数の落ち込みを抑制するローRPMアシストを備えていることも手伝って、タウンユースでも持て余す場面はない。スロットル全閉のままでクラッチをゆっくり繋いでいくと、ミートする瞬間に回転数がわずかに上昇しようとするため、その介入を知ることができる。 ここまではGSX‐Sと同じだが、そのちょっと先にカタナ独自の味つけが施されている。それがスロットルワイヤーの取り回しだ。 GSX‐Sのそれは一般的な真円のプーリーに繋げられ、スロットルグリップを「1」開けば、ワイヤーが「1」引っ張られる。 一方のカタナは真円ではなく、イメージで言えば初期は「1」開いても「0.8」だけ引っ張られ、それが「0.9」、「1」と可変していく形状に変更。最初は穏やかにパワーが立ち上がり、高回転域では本来のレスポンスを発揮する可変タイプになっているのだ。 これが急激に立ち上がるようなら、かえって乗りにくくなるが、そのサジ加減が上手く作り込まれている。いわゆるドン突きの類は一切なく、スロットル開度に従って盛り上がる4気筒らしい、胸のすくエキゾーストノートを楽しむことができる。 とはいえ、これは今回じっくり乗ってみて実感したことだが、新型カタナの美点は、いたずらにスポーツ性を追求したり、無理にそれを演出していないところにある。

5つのセンサーからなるトラクションコントロールを装備。介入度は3段階設定され(数字が増えると滑りやすい路面向き)、OFFも選べる
ディティールへのこだわりがもたらすKATANAらしさ
バイクは趣味性を満たすための乗り物であり、刺激の度合いで語られることが多い。我々のような立場ならなおさらで、試乗の時間が短ければ短いほど、強い印象を残す部分を拾い上げてしまいがちだ。
少々過渡特性に難があっても高回転域にパンチがあればそのアグレッシブさを、少々ハンドリングにクセがあっても高荷重域にスウィートスポットがあるならそのスパルタンさを伝えようとする。
そのマシンが最も輝く領域で走らせ、それを伝える役割を担っているつもりだが、なんの気負いもてらいもなく走らせることができ、それが最初から最後まで続くマシンに時として出会う。新型カタナがまさにそうした1台で、従順なエンジンとニュートラルなハンドリングに身を任せ、ただただ気持ちよく流せるように仕立ててあるのだ。
テスター目線でパーツにフォーカスすれば、タイヤの接地感がもうワンランク向上すればベストだ。そのためにリヤサスペンションのバネレートを下げたり、リンク比を変えるなどの手法を試してみたいが、裏を返せばその程度である。
148PSに達する最高出力を手の内に収め、これほど自在に引き出せるバイクは極めて珍しく、ナチュラルな振る舞いこそが評価されるべきだ。複雑な電子デバイスは備えていないが、それに頼ることなく操れる素性のよさ。それこそがカタナというバイクの真骨頂であり、生真面目なモノ作りを続けてきたスズキらしさが注がれている。
カタナはそのネーミングといい、オリジナルの出自をなぞるような開発エピソードといい、一見するとネオクラシックの時流に乗った企画モノに思われている節があるが、その実態は極めて高い完成度を誇るスタンダードバイクである。
豊かなトルクを生み出すロングストロークのK5ユニットは、その存在を忘れてクルージングすることも、タコメーターの針を躍らせながらそのバイブレーションを全身に浴びることも許容する自在のエンジンだ。
ライダーの望みにいかようにも応えてくれるモデルである、オリジナルがそうであったように長く愛されていくに違いない。]]>