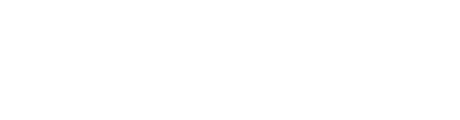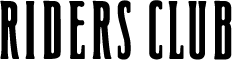「僕にとってWGPのヒーローはケヴィン・シュワンツだった」
ライダースクラブ読者の皆さま、はじめまして。今月から連載することになりました、フォトグラファーの折原弘之と申します。ほとんどの方が僕のことを知らないと思うので、自己紹介がてら経歴を書くところから始めようと思います。
初めてレース撮影に行ったのは1981年の鈴鹿8時間耐久でした。当時メディアセンターはグランドスタンドの最上段にありました。土砂降りのレースだったのですが状況を確認しにメディアセンターに戻ると、最終コーナーで転倒したデビット・アルダナ選手(ヨシムラ)がストレートの真ん中あたりまで滑ってきたのを今でも覚えています。当時はシケインがなかったので、最終コーナーは4速くらいのハイスピードコーナーでした。アルダナ選手は300mくらい滑った後、再びマシンに跨がって走り出しました。
それから84年まで全日本ロードレース、モトクロスを撮影し95年の1月にスーパークロスを撮りに渡米します。この時まだ22歳の若造で、海外に出るのも初めてでした。そこで海外取材慣れしている、憧れのフォトグラファー坪内隆直さんに相談にいきました。すると「アメリカから帰ったらウチに来い」と誘われ、85年の3月から坪内さんに師事することになります。
坪内さんの会社に入り、雑誌『グランプリイラストレイテッド』の、スタッフフォトグラファーとしてWGP、世界耐久選手権、モトクロス、トライアルとあらゆるバイクレースの取材に明け暮れました。その後89年のシーズンオフに同雑誌が休刊。フリーランスとしてWGPを撮りに行く決断をしました。それからは写真を売ったお金で旅費を作り、ほぼ全てをレース撮影に注ぎ込む日々。まったく生活を顧みることなく、夢中でWGPを追いかけました。

そして92年、F1の全ラウンドを撮影する話が舞い込んできて、仕事の中心は四輪へと移って行きました。97年までの5年間は、F1とWGPの両方を追いかける生活になりました。当然日本に帰ってくる暇などなく、ホテルに泊まるお金もありません。3日間のうち2日は車中泊、サーキット併設のシャワーを使って駐車場に泊まる。そんなことをしていた時期もありました。でも、そんな生活に嫌気が差したり、苦しいと思ったことは一度もありません。むしろ毎日がワクワクの連続で、一生この生活が続けば良いのにと思うほどでした。僕にとってWGPとそこにいる人たちが、それほど魅力的で素晴らしい世界でした。
90年ごろから徐々にF1に軸足を置くようになり、97年から2014年までF1漬けの生活になりました。当初は人間味を感じにくいと思い、なかなか馴染めなかった四輪レースですが、突き詰めるとレースの魅力は二輪と違いがないことがわかり、今ではすっかり四輪レース三昧です。
とは言え僕の根っこはやっぱり二輪レースにあります。今でも鈴鹿8耐やモトGP日本ラウンドは撮影に行きます。18歳でサーキットデビューしてから、57歳になった今でも相変わらずレース漬けです。
僕がどんな撮影をしてきたかは、なんとなく分かっていただけたでしょうか。このような生活を送ってきたので、当コラムも当然WGPの話題が多くなってくると思います。その第一回に選んだのがこの写真のケヴィン・シュワンツ選手。初めて渡欧した85年のダブルチャンピオンであるフレディ・スペンサー選手の衝撃も大きかったのですが、僕にとってWGPはケヴィンなんです。「10年に一人の天才」という言葉をよく耳にしますが、80年代の天才がフレディなら、約10年後に現れた90年代の天才がケヴィンだと思います。

初めてケヴィンを見た時、ハングオンはするもののリーンアウトに乗り、股下で暴れるマシンをねじ伏せて走る印象でした。ですがその本質は全く違っていました。それまでにもワイン・ガードナー選手のように、暴れるマシンを抑え込む感じの選手はいました。でもケヴィンのそれは、明らかに違っていました。暴れるマシンを抑え込むのではなく、全て織り込み済みでアンダーコントロールしている感じなんです。当時はトラクションコントロールなどなかったので、スロットルコントロールでパワーを抑制していました。ところが彼は全開にしてリアタイヤのスライドをコントロールしている感じなんです。フレディがWGPに来るまで、バイクはコーナリングフォース、つまりリーンアングルでコーナリングしていました。ところがフレディはスリップアングル、つまりリアタイヤを滑らすことでコーナリングしていたんです。
その事はタイヤの形状の変化が証明しています。それまでのリアタイヤは細く丸みを帯びていたのですが、フレディの出現で現代のタイヤに近い扁平になったのです。そしてそのタイヤの使い方を、一歩進化させて乗っているのがケヴィンのライディングスタイルといった印象です。
ケヴィンのスタイルは、コーナリング前半では誰よりも深くリーンしてきます。そこからクリップにつきアクセルを開けるころには、ほぼ直立と言って良いほどマシンは起きています。マシンが起きているのに旋回しているのは、リアタイヤのスライドを効率よく使っているからです。その証拠に路面にははっきりとブラックマークが残っているのです。つまりマシンを起こして、タイヤを斜め前に滑らせながら立ち上がっていく感じです。ですからリアタイヤが大きくブレイクすることなく、消しゴムで文字を消すようなグリップ感で立ち上がっていく感じです。もう異次元でした。多くの偉大な世界チャンピオンを見てきましたが、GP500のモンスターマシンをこれほど荒々しく、かつ繊細に操るライダーは他に思いつきません。ケヴィン・シュワンツがGPシーンに登場した日から、僕にとって唯一無二のライダーになりました。

折原弘之
1963 年生まれ。’83 年に渡米して海外での撮影を開始。以来国内外のレースを撮影。MotoGPやF1、スーパーGTなど幅広い現場で活躍する]]>
 そして92年、F1の全ラウンドを撮影する話が舞い込んできて、仕事の中心は四輪へと移って行きました。97年までの5年間は、F1とWGPの両方を追いかける生活になりました。当然日本に帰ってくる暇などなく、ホテルに泊まるお金もありません。3日間のうち2日は車中泊、サーキット併設のシャワーを使って駐車場に泊まる。そんなことをしていた時期もありました。でも、そんな生活に嫌気が差したり、苦しいと思ったことは一度もありません。むしろ毎日がワクワクの連続で、一生この生活が続けば良いのにと思うほどでした。僕にとってWGPとそこにいる人たちが、それほど魅力的で素晴らしい世界でした。
90年ごろから徐々にF1に軸足を置くようになり、97年から2014年までF1漬けの生活になりました。当初は人間味を感じにくいと思い、なかなか馴染めなかった四輪レースですが、突き詰めるとレースの魅力は二輪と違いがないことがわかり、今ではすっかり四輪レース三昧です。
とは言え僕の根っこはやっぱり二輪レースにあります。今でも鈴鹿8耐やモトGP日本ラウンドは撮影に行きます。18歳でサーキットデビューしてから、57歳になった今でも相変わらずレース漬けです。
僕がどんな撮影をしてきたかは、なんとなく分かっていただけたでしょうか。このような生活を送ってきたので、当コラムも当然WGPの話題が多くなってくると思います。その第一回に選んだのがこの写真のケヴィン・シュワンツ選手。初めて渡欧した85年のダブルチャンピオンであるフレディ・スペンサー選手の衝撃も大きかったのですが、僕にとってWGPはケヴィンなんです。「10年に一人の天才」という言葉をよく耳にしますが、80年代の天才がフレディなら、約10年後に現れた90年代の天才がケヴィンだと思います。
そして92年、F1の全ラウンドを撮影する話が舞い込んできて、仕事の中心は四輪へと移って行きました。97年までの5年間は、F1とWGPの両方を追いかける生活になりました。当然日本に帰ってくる暇などなく、ホテルに泊まるお金もありません。3日間のうち2日は車中泊、サーキット併設のシャワーを使って駐車場に泊まる。そんなことをしていた時期もありました。でも、そんな生活に嫌気が差したり、苦しいと思ったことは一度もありません。むしろ毎日がワクワクの連続で、一生この生活が続けば良いのにと思うほどでした。僕にとってWGPとそこにいる人たちが、それほど魅力的で素晴らしい世界でした。
90年ごろから徐々にF1に軸足を置くようになり、97年から2014年までF1漬けの生活になりました。当初は人間味を感じにくいと思い、なかなか馴染めなかった四輪レースですが、突き詰めるとレースの魅力は二輪と違いがないことがわかり、今ではすっかり四輪レース三昧です。
とは言え僕の根っこはやっぱり二輪レースにあります。今でも鈴鹿8耐やモトGP日本ラウンドは撮影に行きます。18歳でサーキットデビューしてから、57歳になった今でも相変わらずレース漬けです。
僕がどんな撮影をしてきたかは、なんとなく分かっていただけたでしょうか。このような生活を送ってきたので、当コラムも当然WGPの話題が多くなってくると思います。その第一回に選んだのがこの写真のケヴィン・シュワンツ選手。初めて渡欧した85年のダブルチャンピオンであるフレディ・スペンサー選手の衝撃も大きかったのですが、僕にとってWGPはケヴィンなんです。「10年に一人の天才」という言葉をよく耳にしますが、80年代の天才がフレディなら、約10年後に現れた90年代の天才がケヴィンだと思います。
 初めてケヴィンを見た時、ハングオンはするもののリーンアウトに乗り、股下で暴れるマシンをねじ伏せて走る印象でした。ですがその本質は全く違っていました。それまでにもワイン・ガードナー選手のように、暴れるマシンを抑え込む感じの選手はいました。でもケヴィンのそれは、明らかに違っていました。暴れるマシンを抑え込むのではなく、全て織り込み済みでアンダーコントロールしている感じなんです。当時はトラクションコントロールなどなかったので、スロットルコントロールでパワーを抑制していました。ところが彼は全開にしてリアタイヤのスライドをコントロールしている感じなんです。フレディがWGPに来るまで、バイクはコーナリングフォース、つまりリーンアングルでコーナリングしていました。ところがフレディはスリップアングル、つまりリアタイヤを滑らすことでコーナリングしていたんです。
その事はタイヤの形状の変化が証明しています。それまでのリアタイヤは細く丸みを帯びていたのですが、フレディの出現で現代のタイヤに近い扁平になったのです。そしてそのタイヤの使い方を、一歩進化させて乗っているのがケヴィンのライディングスタイルといった印象です。
ケヴィンのスタイルは、コーナリング前半では誰よりも深くリーンしてきます。そこからクリップにつきアクセルを開けるころには、ほぼ直立と言って良いほどマシンは起きています。マシンが起きているのに旋回しているのは、リアタイヤのスライドを効率よく使っているからです。その証拠に路面にははっきりとブラックマークが残っているのです。つまりマシンを起こして、タイヤを斜め前に滑らせながら立ち上がっていく感じです。ですからリアタイヤが大きくブレイクすることなく、消しゴムで文字を消すようなグリップ感で立ち上がっていく感じです。もう異次元でした。多くの偉大な世界チャンピオンを見てきましたが、GP500のモンスターマシンをこれほど荒々しく、かつ繊細に操るライダーは他に思いつきません。ケヴィン・シュワンツがGPシーンに登場した日から、僕にとって唯一無二のライダーになりました。
初めてケヴィンを見た時、ハングオンはするもののリーンアウトに乗り、股下で暴れるマシンをねじ伏せて走る印象でした。ですがその本質は全く違っていました。それまでにもワイン・ガードナー選手のように、暴れるマシンを抑え込む感じの選手はいました。でもケヴィンのそれは、明らかに違っていました。暴れるマシンを抑え込むのではなく、全て織り込み済みでアンダーコントロールしている感じなんです。当時はトラクションコントロールなどなかったので、スロットルコントロールでパワーを抑制していました。ところが彼は全開にしてリアタイヤのスライドをコントロールしている感じなんです。フレディがWGPに来るまで、バイクはコーナリングフォース、つまりリーンアングルでコーナリングしていました。ところがフレディはスリップアングル、つまりリアタイヤを滑らすことでコーナリングしていたんです。
その事はタイヤの形状の変化が証明しています。それまでのリアタイヤは細く丸みを帯びていたのですが、フレディの出現で現代のタイヤに近い扁平になったのです。そしてそのタイヤの使い方を、一歩進化させて乗っているのがケヴィンのライディングスタイルといった印象です。
ケヴィンのスタイルは、コーナリング前半では誰よりも深くリーンしてきます。そこからクリップにつきアクセルを開けるころには、ほぼ直立と言って良いほどマシンは起きています。マシンが起きているのに旋回しているのは、リアタイヤのスライドを効率よく使っているからです。その証拠に路面にははっきりとブラックマークが残っているのです。つまりマシンを起こして、タイヤを斜め前に滑らせながら立ち上がっていく感じです。ですからリアタイヤが大きくブレイクすることなく、消しゴムで文字を消すようなグリップ感で立ち上がっていく感じです。もう異次元でした。多くの偉大な世界チャンピオンを見てきましたが、GP500のモンスターマシンをこれほど荒々しく、かつ繊細に操るライダーは他に思いつきません。ケヴィン・シュワンツがGPシーンに登場した日から、僕にとって唯一無二のライダーになりました。
 折原弘之
1963 年生まれ。’83 年に渡米して海外での撮影を開始。以来国内外のレースを撮影。MotoGPやF1、スーパーGTなど幅広い現場で活躍する]]>
折原弘之
1963 年生まれ。’83 年に渡米して海外での撮影を開始。以来国内外のレースを撮影。MotoGPやF1、スーパーGTなど幅広い現場で活躍する]]>