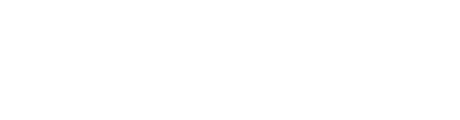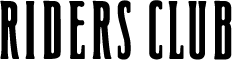MotoGPマシンから市販車まで貫かれる、”ライダー最優先の開発思想”|GSX-S1000GT&Hayabusa

最新のGSX-S1000GTやHayabusaを走らせた青木宣篤さんが、満足げに頷く。そして、「どのバイクにも、しっかりと受け継がれているものがあるね」と笑った。それは、レーシングマシンの世界最高峰、MotoGPマシンの開発から得られた知見。青木さん自身が、開発ライダーとして積み上げ、残してきたものだ。
スズキは常に謙虚で慎重に開発を進める
私が所有しているスズキ・ハヤブサは、’99年に発売された初代だ。だから正確には「GSX1300Rハヤブサ」ということになる。
他にない独特なデザインに魅せられた私は、発売と同時にこの1300㏄ビッグバイクを購入した。だが、忙しくて乗る時間がなかった。
ハヤブサでサーキットを走るでもなく、ツーリングに行くでもない。ハヤブサは、ただガレージの肥やしになっていた。当時の私は、スズキ・グランプリチームのファクトリーライダーとして、世界グランプリ500㏄クラスを戦っていたのだ。

’97年まではホンダのサテライトチームで世界グランプリを戦っていた私だったが、’98年に向けては、スズキとレッドブル・ヤマハ・WCMからオファーがあった。 スズキはファクトリーチーム、そしてヤマハはサテライトチームだ。私のレース人生で初めてのファクトリーチームが、目の前にある。もちろん私は、スズキを選んだ。
スズキのGPファクトリーチームには、実に多くのスタッフがいた。いろいろな人が、いろいろなことを考えてくれる。それまでのサテライトチームでは、チーフメカニックがひとりでほとんどのことを考え、決めていたのとは対照的だった。言うまでもなく、スタッフは多い方がいい。関わる人が多いほど、多くの優れたアイデアが出てくるからだ。
スズキのファクトリーライダーとしてグランプリを戦い始めた’98年、私は27歳だった。憧れていたファクトリーチームの一員になり、自分が望むパーツはすべて用意された。
「これはすごい……」と感動する一方で、プレッシャーも大きかった。ファクトリー体制でありながら、スズキのスタッフたちは常に謙虚だった。どんなにいいマシンを作っても、なかなか思うような結果が出せない私に対してさえ「ウチはこんなのしかできないからさ……」と言うのだ。
「申し訳ないけど、これで頑張ってくれない?」という調子だ。
メーカーによっては、「ウチのバイクが世界一。これで結果を出せなければライダーの問題」というところもある。スズキの謙虚さには、良し悪しの両面があると思うが、ライダーファーストの開発姿勢はとてもやりやすかった。
スズキのファクトリーチームに所属し、2ストローク500㏄マシン、RGV-Γを走らせたのは3シーズンだ。この間に得たものは多かった。
特に、当時は車体エンジニアだった河内健さんから教わった知識は、今も財産だ。河内さんはいろいろな車体セッティングを提案してくれた。そして実際に走っての印象は、ほぼ河内さんの想定していた通りだった。
ファクトリーマシンはセッティング幅が広い分、一度迷路に迷い込むとなかなか抜け出すことができない。その点、河内さんは信頼できるエンジニアで、大いに助かった。河内さんは典型的なスズキパーソンで、セッティングも決してゴリ押しはしない。
「こうしたらどうかなあ」という遠慮がちな提案だ。しかも、いつも「大丈夫かなあ」と慎重だった。そんな河内さんとだったからこそ、私は安心して車体セッティングを進めることができた。
’98年はランキング9位、’99年は13位、そして’00年は10位。4位は6回あったが、レースの神様はオマケをくれることがなく、表彰台に立つことはできなかった。特に’00年はチームメイトのケニー・ロバーツ・ジュニアがチャンピオンになっている。いくらスズキのスタッフが謙虚とはいえ、私の肩身は狭かった。
セッティングはゴリ押しではなく〝提案〟だった
’01年はブリヂストン・MotoGPタイヤの開発ライダーを務めた。’02〜’04年はケニー・ロバーツ(父)が率いるプロトン・チームKRでMotoGPを戦ったが、残念ながら成績は振るわず、’05年はMotoGPのシートが無さそうだった。
スーパーバイク世界選手権という話もあったが、33歳で「自分はまだやれる」と信じていた私は、MotoGPの舞台から離れたくなかった。そこで、スズキに開発ライダーとして自分を売り込むことにした。
開発に回ることは、自分が落ち目になったようで寂しさはあったが、「どんな形でもMotoGPに関わっていれば選手として戻るチャンスがあるだろう」と思っていた。
スズキのチームマネージャーだったギャリー・テイラーさんに直接電話すると、「そうか、分かった。じゃあ本社に掛け合ってみるよ」とアッサリ言った。
拍子抜けするほどポンポンと話が進み、’04年末には早くもスズキ・MotoGPマシンの開発ライダーとしてテスト走行することになった。マレーシアのセパンで、初めてスズキの4ストロークMotoGPマシン、GSV-Rを走らせた私は、衝撃を受けた。問題だらけだったのだ。エンジンパワーは明らかに不足していた。車体も重心が低いだけでフロントタイヤに十分な荷重がかからないなど、課題は多かった。実際、’02年から’04年に至るまで、GSV-Rはめざましい成績を残せずにいた。
パワー不足を指摘すると、スズキはすぐにパワーアップに取り組み、ほんの2〜3カ月でカムシャフトを作り直すなどした新スペックのエンジンを用意してきた。やる気が見え、こちらもモチベーションが上がった。
【2005|GSV-R(990cc)】開発ライダーとしてのキャリアが始まる

ただ、レーシングマシンのエンジンはただパワーがあればいいわけではない。レースの現場を視察すると、とにかくエンジンの調整に時間がかかっていることが見て取れた。
スロットルを開けると、「ドン!」と想定以上の加速をしてしまう。逆に、想定以下の加速しかしない場面もある。時間のないレースウィーク中に、エンジンのベースセッティング出しに追われ、本来やるべきである「速く走るためのセッティング」にまで至っていなかった。
’06〜’07年にかけて、GSV-Rのドライバビリティを改善していった。この頃のMotoGPマシンは電子制御が急速に進化し、エンジニアも「電子制御で何でもできる」あるいは「何でもしたい」と思いがちだった。
しかしその結果、エンジンの素性から起きている問題点を、電子制御で覆い隠すようになってもいた。言い方は悪いが、「臭いものにフタをする」という状態だったのだ。「ここが課題だな」と気付くと、さっそく指摘を始めた。
【2006|GSV-R(990cc)】ターゲットは「エンジンの洗練」

当時、私の他に秋吉耕佑が開発ライダーを務めていた。彼は「出汁が出ていません」という独特な言い方をしていた。
料理のもっとも基本となる出汁が出ていないのに、塩だ醤油だと調味料を足したところで、本当の旨味は出せない、というニュアンスだ。
ライダーは、しばしばこういった感覚的なコメントをするものだ。乗って感じていることだから、決して間違いではない。しかし、スズキの真面目なエンジニアにはその真意がなかなか伝わらなかった(笑)。
「ライダー語」は、エンジニアにも伝わる言葉にきちんと翻訳しなければ、問題解決に辿り着けない。自分自身も含め、走行フィーリングをいかに分かりやすい言葉で表現するかに心を砕いた。
【2007|GSV-R(800cc)】エンジニアに伝えるための道具「言葉」を獲得していく

エンジンは徐々に素から作り直されていったが、今度は車体の問題が浮き彫りになり始めた。ブリヂストンタイヤとのマッチングに苦労し、パフォーマンス不足に陥っていたのだ。だが、どこをどうすればいいのか分からずにいた。
悩みに悩んでいた時、ライバルメーカーのマシンの走りを観察していたら、フレームがフニャフニャであることに気付いた。アルミ製フレームが「フニャフニャ」とはおかしな表現だが、フレームはごくわずかだが確実に動く。そして、それをライダーは敏感に感じ取る。
【2008|GSV-R(990cc)】タイヤとシャシーのマッチングに苦しむ

外から見ていてもっとも分かりやすかったのは、ウイリーから着地する際だ。ライバルメーカーのマシンは、トンと着地した時、明確にフレームがねじれていた。
「これだ!」
フレームまわりの大改革に着手した。まずお願いしたのは、左右のメインフレームをつなぐクロスメンバーをぶった切ることだった。
スズキのエンジニアたちは、「そんなの無理だよ」と嫌がった。クロスメンバーは高いフレーム剛性を生み出す要のような部位だ。レーシングマシンであっても安全性を何よりも重視するスズキにとって、そこにメスを入れることなど御法度だった。
それも当然だ。「ハイパワー、ハイスピードであるほど、バイクのフレーム剛性は高くあるべき」と、長く信じられていたのだ。
じっくりと時間をかけて説得し、ようやくクロスメンバーをカットしてもらえた。結果、フレームはわずかにねじれる動きを見せ始めたが、正直なところ期待していたほど劇的な変化ではなかった。
【2009|GSV-R(990cc)】シャシーに大ナタを振るう

「フレーム全体の剛性が高すぎる」
フレームの裏側にどんどん穴を開け、剛性を落としてもらった。
「これ以上の穴開けは不可能」というところまで追い込んでも、まだ十分なねじれが得られない。新しいフレームを作った。穴を開けられるだけ開けて、まだ剛性が高すぎるので、フレームを作り直す。そんなことを3回ほど繰り返し、ようやく「これならいいね」というフレームに辿り着いた。
頑丈で壊れない骨格でしかなかったフレームが、ついに「旋回力を高める武器」に仕上がったのだ。この頃には車体の解析技術も進歩し、適度なねじれやしなりが発生しながらも、スズキが納得できる安全性を両立するフレームが完成したのだった。
このフレームに搭載されたエンジンは、ひときわ煮詰められ、洗練されていた。スロットルの開け始めから全開の高回転域まで、望むだけのパワーが得られるエンジンだ。
優れたフレームとエンジンを組み合わせた’11年のスズキGSV-Rは、最高の仕上がりだった。
【2011|GSV-R(990cc)】コンパクトな参戦体制ながら、極めて高い完成度を誇った

’12年から、スズキはMotoGP参戦を休止する。しかし’15年の復帰をあらかじめ宣言しており、水面下での開発は小規模な体制ながら高いモチベーションで推し進められていた。
私も引き続き開発ライダーを務めさせてもらい、足繁く静岡・竜洋テストコースに通った。
エンジン型式はそれまでのV型4気筒から直列4気筒にスイッチしていた。量産車開発との連携を深める狙いだ。そして、もともとスズキにはGSX-R1000があった。MotoGPマシンとスーパースポーツは、より密接な関係になった。
【2013|GSX-RR(1000cc)】来るべき復帰の時をめざし、地道な開発を着実に続ける

GSX-RRと名付けられた直4MotoGPマシンのエンジンは、パワフルさと扱いやすさが高次元でバランスし、最初からある程度いい仕上がりだった。フレームもどんどん進化し、より攻めた設計になっていた。
2ストローク500㏄マシンで争われていたグランプリが、4ストロークのMotoGPになって10年以上。その間は、苦労と苦戦の連続だった。しかし、スズキはMotoGPを戦いながら多くのものを蓄積していた。
【2014|GSX-RR(1000cc)】翌年の復帰に向けてマシン開発と体制強化、プロモーションが加速

開発ライダーとしてスズキのエンジニアたちと深く触れ合って思うのは、つくづくライダーファーストだということだ。シーズンが変わり、スタッフが変わっても、ライダーを優先する姿勢は変わらなかった。ライダーの言葉に耳を傾け、ライダーの意に沿おうとしてくれた。だから安心して、マシンに身を委ねられる。
【2016|GSX-RR(1000cc)】翌復帰後の初優勝はM.ビニャーレスが達成

これは最近のスズキ量産車にもそっくり当てはまることだ。ライダーの意のままになるという安心感があるからこそ、スポーツライディングを心ゆくまで満喫できる。
MotoGPマシンからフィードバックされたものばかりではないだろう。だが、何らかの形で生きていることは間違いない。どのバイクにもGSX-RRに似た方向性を感じるのだ。
【2019|GSX-RR(1000cc)】ロッシやマルケスを下すA.リンスの快進撃

’20年、ジョアン・ミルがタイトルを獲得した。素晴らしい成果だが、同じぐらいうれしいのは「GSX-RRの完成度の高さはMotoGP随一」と、関係者や、ライバルのMotoGPライダーたちさえもが高く評価してくれたことだ。自分がその一翼を担えたかと思うと、誇りに思う。
そして乗り手を選ばず、幅広い場面で乗りやすいスズキの量産車を走らせるたびに、わずかでもこの仕上がりの役に立てたのかなと、大きな喜びを感じる。
【2020|GSX-RR(1000cc)】安定した走りで混乱を制し、20年ぶりのタイトルを獲得

(青木宣篤)