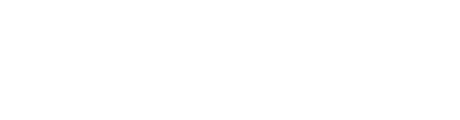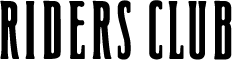【パドックから見たコンチネンタルサーカス】紡がれてきた鈴鹿8耐の狂気

レース撮影歴約40年の折原弘之が、パドックで実際に見聞きした四方山話や、取材現場でしか知ることのできない裏話をご紹介。
鈴鹿8時間耐久ロードレース。言うまでもなく、日本で行われる最高峰の二輪レースだ。レース自体は本来、世界耐久選手権シリーズの中の1レースにしか過ぎない。歴史や格式で言えば、ル・マン24時間やボルドール24時間に比べれば足元にも及ばない。だが今も、世界中のトップライダーが「出たい」と思うレースである。
なぜ鈴鹿8時間耐久が、それほどのレースになったのか。それは二輪大国である日本の、しかもホンダのお膝元である鈴鹿で行われたこと。そして日本のバイクメーカーが威信をかけ、こぞって優勝を狙いに来たからに他ならない。
’78年に初開催した同大会は、最初の数年は世界耐久の中の1レースといった感が強く、エントリーするライダーもシリーズを追うチームがほとんど。そこにヨシムラとホンダファクトリーがスポット参戦し、トップ争いをしていた程度だった。

自国のスターライダーが出るというのは、ル・マン24時間やボルドール24時間でも見られたことで、さほど特別感はなかった。ところが’85年にヤマハ・ファクトリーが資生堂テック21をスポンサーにつけ、平忠彦/ケニー・ロバーツによるドリームチームを結成。
この年あたりから、鈴鹿8時間耐久は大きく変わっていった。このドリームチームに呼応するように、ホンダやヨシムラが世界のトップライダーを呼び寄せる。もちろん国内のトップライダーも駆り出され、メーカーの威信をかけた一大イベントへと変貌した。資生堂の参戦によりスポット参戦するファクトリーチームには、多くの有名企業がスポンサーとなる。ファクトリーチームは、自社の威信に加えスポンサー企業への責任も背負うことになる。そして平忠彦氏が語るように、「優勝がファクトリーチームの最低条件」になった。
「レースで勝つのはもちろん、ポールポジションを獲ることも求められましたね。当然、それを実行できるだけのマシンも用意してもらいました」と語ったのは’90年代の8耐で活躍した岡田忠之氏。優勝が前提のファクトリーチームはポールポジションやラップレコードなど、そのすべてを手に入れようと躍起になった。
そこで白羽の矢が立ったのが、グランプリライダー達だ。右の写真は’89年の8耐スタートシーン。マイケル・ドゥーハンを先頭にウエイン・レイニー、ジョン・コシンスキーの姿が確認できる。それぞれのパートナーは、ワイン・ガードナー、ケビン・マギー、平忠彦だ。さらにケビン・シュワンツも出走しており、5人のワールドチャンピオンがエントリーしていた。
もちろん数多くの国内トップライダーもエントリーしている。現在の8時間耐久とは比べ物にならないほど、豪華なライダー達が結集し、本気で優勝を目指していたのだ。そして彼らは、鬼神のような走りで鈴鹿のラップレコードを更新していった。その弊害として、転倒の憂き目に合うグランプリライダーも少なくないほど、全開のアタック合戦を繰り広げた。その光景は、あたかもグランプリのポール争いと見紛うばかりだった。
通常グランプリシーズンの真っ只中に、スポット参戦の耐久レースでこれほどリスクを犯すレースなどありえない。ワールドチャンプを争うライダーにすれば、正気の沙汰とは思えない事態だ。まさにこの狂気が鈴鹿8時間耐久を、特別なレースにしたと言えるだろう。数多くのグランプリライダーとメーカーが、30年以上に渡り紡いできた狂気の歴史。それが鈴鹿8時間耐久の歴史なのだ。


そんなストーリーを知っていれば、その歴史に名を刻みたいと思うのも当然の成り行きなのだろうか。’00年以降、エントリーするトップライダーは減ってきたものの、今も8耐の歴史は繋がっている。昨今ドゥカティのファクトリライダー達が、こぞって出場を望んでいるという噂もある。もしかしたら今後、ドゥカティのファクトリーがエントリーし、日本のメーカーが迎え撃という光景が見られるかもしれない。そんなことになれば、’80年代の狂気が再び見られるかもしれない。そんな日が来ることを、期待せずにはいられない。