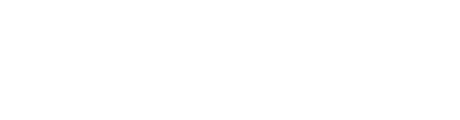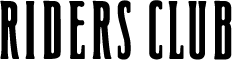これぞ加速の権化! 新型CBR1000RR-R FIREBLADE SP サーキット試乗

Honda CBR1000RR-R FIREBLADE SP ホンダ伝統のスーパースポーツ「CBR1000RR」がフルモデルチェンジを受け、その名も「CBR1000RR-R」としてデビュー。本誌ではすでに幾度かインプレッションをお届けしているがその真骨頂ともいうべきサーキット仕様車が本当の姿だった。
全開の“アールアールアール”
7月13日、ツインリンクもてぎの東コースにて新型CBR1000RR‐R(以下RR‐R)の試乗会が開催された。サーキットのメインゲートを通過した後、さらにふたつのゲートが設けられるなど、どこか物々しいのはコロナの影響だけではないだろう。
なぜなら試乗車両はサーキット仕様になっており、走行毎にコースインするのは3台のみだ。招待されたメディアもかなり絞られ、暗に「プロ、もしくはそれに準ずるライダー限定」の雰囲気が漂っていた。ピットに並べられたトリコロールカラーのRR‐Rはレーシングスタンドでリフトアップされ、タイヤにウォーマーが巻かれた状態で準備が進められていた。
本来、純正装着されるのはピレリの「ディアブロ・スーパーコルサSP」か、ブリヂストンの「バトラックスRS11」のどちらかなのだが、今回は全車ピレリの「ディアブロ・スーパーコルサSCV3」に交換されている。

タイヤはピレリのスリックに一番近い「ディアブロ・スーパーコルサSC V3」に換装され、グリップ力が最大限確保された
このタイヤは、スーパーバイク世界選手権のオフィシャルタイヤ「ディアブロ・スーパーバイク(=スリック)」に次ぐ性能を誇り、デリバリーが始まって間もない製品だ。わざわざそれが用意されたのは、「218psの最高出力を思う存分引き出してください」という開発陣の意図に他ならず、限界域でも破綻しないという自信が伺える。
思い出したのは、19年のEICMAでの一幕だ。RR‐Rの開発責任者を務める石川譲さんに、「RRまではワインディングに軸足を置いていたのに、なぜRR‐Rは一転してサーキット最速を押し出しているのか?」とたずねた時のことだ。
曰く、「欧米でも日本でもスーパースポーツを楽しまれるお客様のメインステージはワインディングでした。しかしながら現在は気軽に楽しめるレースが増え、ストック状態でいかに高いポテンシャルを持つかが問われるようになり、結果的にシェアを左右します。我々としてはホンダを選んでくださったユーザーの後押しをしたいと考え、徹底してベースマシンのポテンシャルアップを図ったというわけです」(石川さん)
サーキットというステージ、装着されたレース対応のハイグリップラジアル、マシンから取り外された保安部品。つまり目の前にあるこの状態が、ホンダが想定するRR‐Rの実像と言っていい。果たしてその狙いにズレはないのか? ここからは宮城光の声を通して、そのパフォーマンスをお届けしよう。
「ウィークポイントを見つけるつもりで走ったのに指摘するような箇所がどこにもない……」(宮城)
鈴鹿サーキットから筑波サーキットのコース1000まで、RR‐Rではすでに大小さまざまなコースを経験している。その意味でポテンシャルの高さは充分知っているつもりだったが、いずれもマージンを充分確保した上での検証だった。
それに対して今回は、コースレイアウトも足まわりも限界を探るのにふさわしい環境が用意された。それゆえ、こちらも職業ライダー的なテンションで試乗に臨むことになったわけだが、言い方を変えると、可能な限りアラを見つけ、それをいかに正確に改善ポイントとしてフィードバックできるか。それが問われる場面だ。
その意味で最初からダメ出しありきでコースインしたと言っていい。 ところが、である。ありとあらゆる場所でスロットルを全開にし、ブレーキもサスペンションも可能な限り追い込んでみたものの、ほとんどなにも起こらないのだ。
ストレートでは異常と表現できる勢いで車速が伸び、なのにタイヤからはしっかり接地感が伝わってくる。最高速付近ではどんなバイクもクルマも車体がリフト気味になるものだが、RR‐Rにはその気配がない。ダウンフォースというより、前方から後方にかけて空気が整流されていることがよく分かる。
仕事柄、ホンダコレクションホールのレーシングマシンに度々乗る機会があるが、少し前の8耐マシンそのものだ。1速で180km/hに達するエンジンの加速感は、四輪のF1的ですらある。
先代モデルよりハイギアード化され、緩慢になっているはずなのにそう思えるのだ。開発責任者代行の細川さんにそれを伝えると、「先代モデルのレースキット装着車よりパワーが出ているので、エンジンには自信があります。それを活かすために徹底しているのが空力で、例えばリアフェンダーもそのひとつ。上面が半円状にカットされているのには理由があり、これによってタイヤの回転が巻き起こす乱流を軽減しています。泥除けのカタチをしていますが、事実上のエアロパーツですね(笑)」
エンジン、空力とくれば次に気になるのが車体と電子制御だ。等間隔爆発で15000rpmを優に超え、218psを発生するということは、本質的にはピーキーなはずだが、スイングアームが伸ばされ、安定方向に振られたディメンションとトラクションコントロールを中心とするデバイスがフォロー。各種設定はデフォルト値のままでなんの問題もなく、サーキットなら最もスポーティなモード1に任せておけばいい。パーソナルなセッティングを施していって、なにかが改善されるほど次元は低くないからだ。
「車体設計そのものでスタビリティが確保できたため、電子制御の介入は先代モデルよりも少なく、もしくは遅らせることができました」(細川さん)

開発責任者代行として1000RRや600RRの動力性能の目標設定などを担当
あまりに高いこのスタビリティは、ライダーによっては鈍さに感じるかもしれない。もしそうなら、ライディングスキルをワンランク上げるチャンスに他ならない。なぜなら、開ける・止める・曲げるという入力をきっちりできるようになった時、その鈍さがリニア感やダイレクト感に変わっているに違いないからだ。
ストリートも快適にこなし、荷物の積載性にも優れ、足つきも良好で……というような80点主義に走ることなく、清々しいほどに割り切った仕様がこのRR‐Rである。
「MotoGPマシンやRC213V‐Sのノウハウを可能な限り盛り込み、RR‐Rはこうあるべきというコンセプトに対してブレることなく開発することができました。外乱に惑わされることなく、一歩先を見据えて作り上げましたからサーキットを思いっきり走って、このパワーを感じて頂けるといいですね」(石川さん)

’08年型CBR1000RRから開発責任者として手腕を発揮。RC213V-Sも担当した
ダウンヒルストレートを全開で駆け下りてもビクともしないステムを見た時、開発陣が真摯に取り組んできたことを確信することができた。