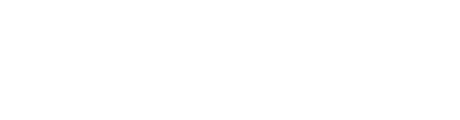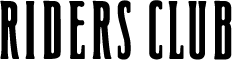元MotoGPライダー中野真矢 スペシャル・インタビュー まっすぐに走り続ける

’97年にプロのレーシングライダーとなって以来、中野真矢は13年にわたり、バイクを戦いの武器にして、真摯に生きてきた。多くの人たちが彼を支え、押し上げた そして今、人々に、そしてバイクという乗り物に、恩返しを続けている。
Shinya Nakano’s life with motorcycle,racing, and people バイクで風と戯れる幸福を噛み締めています
初めて走らせる乗り物を前に、少年はワクワクしていた。好奇心旺盛な5歳の男の子が、本格的なポケバイに乗ろうとしているのだ。興奮するのも無理はなかった。 だがエンジンがかかると、耳をつんざく迫力ある音に少年はすっかり驚き、たじろいでしまった。
この乗り物は、少年が期待していた「楽しいオモチャ」とはあまりにかけ離れている。ついには「もう帰る〜」と、泣き出した。 大きな瞳からぽろぽろ涙をこぼしたその少年――中野真矢は、後にMotoGPライダーとなる。涙を拭いてポケバイにまたがったことが、すべての始まりとなった。
「いざ走り始めたら、意外と楽しかったんですよ(笑)」 エンジン音は怖かったが、ポケバイで走ること自体は面白そうだ。この時に乗ったのは借り物のポケバイだったが、さっそく自分のポケバイを買ってもらうことになった。 ところが、まだ試練が待っていた。父・満さんが畳の上に1万円札を12枚並べてこう言ったのだ。
「いいか、ポケバイにはこれだけのお金がかかるんだ。本気でやるんだぞ」 中野少年には、まったくわけが分からなかった。何しろ5歳だ。12万円の意味など理解できるはずもない。だが、「なんかすごいことなんだな」ということは実感できた。 「子供心に『生半可じゃねえな』と思った……んじゃないですかねえ。正直、ちっちゃい頃の話だからよく覚えてないんですけど(笑)」
いずれにしても、中野少年の心には「バイクはすごい」という思いが深く強く刻み込まれ、中野真矢という人間の礎になった。「矢のようにまっすぐ育て」という願いを込めて名付けられた「真矢」という名のままに、まっしぐらにバイクの道を突き進むのだった。
爽やかな笑顔で、いつしか「王子」というニックネームで呼ばれるようになった中野だが、実態はかなり異なる。要所要所で失敗し、壁に突き当たり、情に突き動かされながら、泥臭くキャリアを重ねてきた。 ミニバイクからロードレースへのステップアップを狙っていた際、名門プライベーターチーム、SP忠男レーシングチームの鈴木忠男社長が中野のミニバイクレースを視察に来た。
「オレの人生が懸かってる。優勝しかない!」と熱くなった中野は、トップを走るライダーを無理矢理抜き、勢い余ってフッ飛んだ。 「終わった……」と思ったら、後日、家に大きな箱が届いた。訝しがりながら開けると、中身は目玉が描かれたヘルメット。勢いが買われ、SP忠男レーシングチームに入れた。
……入ったものの、若手の登竜門である鈴鹿4耐に向けてのウインターテストでTZR250に乗ると、チームメイトの山内俊児がピットロードでいきなり転倒した。「こりゃもうクビだわ……」と思っていたら、中野自身も1コーナーで転んだ。ふたりとも、冬の新品タイヤの扱い方がまったく分かっていなかった。 そのペアが’94年鈴鹿4耐で優勝を果たした。スマートとはほど遠かったが、勢いはあったのだ。しかも、その勢いが並大抵ではなかった。
1994年鈴鹿4耐優勝

中野は翌’95年から全日本ロードGP125クラスに参戦開始。97年にはヤマハファクトリー入りを果たしてGP250にステップアップすると、98年にはチャンピオンを獲得し、99年から世界グランプリを舞台に戦うようになった。凄まじい勢いで駆け上ったのだが、中野自身にその自覚はない。
むしろ、「多くの人との出会いが自分を支えてくれたからこそ」と、感謝を口にする。 「ヤマハ全日本時代にはシャケさん(河崎裕之氏)が監督で、たくさんのことを教わったんです。それまでずっと独学だった僕が、ライダーとしての基礎を学んだ時期でした。GPでは最初の4年間、テック3に在籍しましたが、それもエルベ・ポンシャラルというフランス人オーナーに認めてもらえたから。それに彼には家族のように大事にされて、ヨーロッパのライフスタイルに触れさせてもらったんです」
人に支えてもらいながら、中野は「自分を必要としてくれる人のために、全力を尽くす」という生き方を身に付けていった。そのベースにあるのは、熱意だ。 カワサキファクトリーチーム入りは、「日本人ライダーとして、日欧の架け橋となりながらマシン開発をお願いしたい」というオファーに熱い思いを感じてのことだった。 その後のコニカミノルタホンダからのオファーにも、ホンダのマシンに日本のスポンサーを付けて走ることに魅かれた。ヨーロッパで暮らすうちに、大和魂がたぎっていた。王子というイメージとは違い、中野は思いで動く人情の男なのだ。



世界GP500ccクラスで新人賞獲得

’01 年は最後の2スト500時代を戦い、ドイツGPで表彰台に。ランキング5位で新人賞に輝いた。’02年、4ストGPマシンが登場すると、未経験のエンジンフィーリングに苦しむ。’03 年はダンティンヤマハに移籍するもランキング10位
グレシーニホンダでの’08年、チェコGPで「自分としてはこれ以上ない走り」をして、4位に入った。喜ぶチームを横目に、中野は「もうダメだ」と自分を見切っていた。最高の環境を与えられ、自分でも最高の走りをしたのに、4位。引き際だと思った。その年を最後にGPを去り、スーパーバイク世界選手権にスイッチした。
「開幕戦からして全然ダメで、レース1は15位、レース2は12位。プライドはズタボロでした(笑)。若くて速いライダーばかりで、年齢も含め限界を感じてましたね」 GPでレース経験があり、得意としていたバレンシアサーキットで、巻き返しを図った。しかし「予選でオイルに乗ってしまい、大転倒して鎖骨をバキバキに折ったんです。一緒に心も折れました(笑)」 ’09年をもって現役引退を決めた。最後の最後まであがき、ボロボロになり、決してスマートとは言えないライダー人生だった。
MotoGPではカワサキファクトリーチームで表彰台に立つ


2009年のスーパーバイク 世界選手権参戦をもって現役引退

MotoGP参戦中に、バイクアパレルブランド「56デザイン」を始めた。世界で戦いながらヨーロッパの優れたデザインに触れ、魅了されていた。’12年には「56レーシング」を発足し、若手育成に力を注ぐ。 ヨーロッパの文化に触れさせてくれたエルベ・ポンシャラルや、ライダーとしての基礎を教えてくれた河崎裕之、そしてライダーとしての可能性を見出してくれた鈴木忠男ら、多くの人が中野に多くを授けた。
それらを今、彼なりのやり方で還元しようとしている。 「ずっとレースをしてきましたが、引退して、自分はバイクそのものが好きだったことに気付いたんです。自分を育ててくれたバイクの世界に、少しでも恩返しがしたい」 今は、ラップタイムに追われることなくバイクに乗れる喜びを感じながら、ツーリングやメディアへの出演、そしてインプレッションなどを楽しむ。
56デザイン代表という責任のある立場で会社の舵取りをしながらも、やはり根はただのバイク好き。5歳の時の感動のままに、そしてバイクへの熱い思いのままに、泥臭く歩み続けようとしている。
56レーシングで若手育成中
「速く走る必要がないって、本当に素晴らしいです。レースをしている時、風は自分の前にそびえ立つ壁のような存在でした。それを乗り越える楽しさもあったけど、やはりしんどさもあった。でも今は、キザかもしれないけど、バイクで風と戯れることができる。その幸福を噛み締めています」 さらりと言ってのけるあたり、やはり王子なのかもしれない。