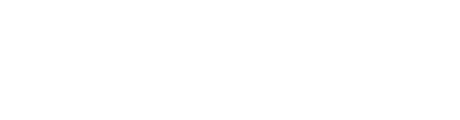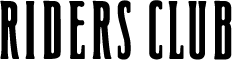フォトグラファー折原弘之が振り返る パドックから見たコンチネンタルサーカス

’81年から国内外の二輪、四輪レースを撮影し続けている折原弘之が、パドックで実際に見て、聞いたインサイドストーリーをご紹介。今月は、原田哲也さんが語った、極限のライン取りについて。

1963年生まれ。’83 年に渡米して海外での撮影を開始。以来国内外のレースを撮影。MotoGPやF1、スーパーGTなど幅広い現場で活躍する。

写真右端:’70年生まれ、千葉県出身。言わずと知れた’93 年の世界GP250ccクラスチャンピオンにして、本誌エグゼクティブアドバイザー。折原とは現役時代から親交のある旧知の仲で、引退後の現在も、本誌の撮影だけでなくプライベートでも交流を続けている。
アプリリアのマシンについて、原田さんに取材をしていた時のことだった。マシンのことやレースのことを振り返ってもらい、一通り取材が終わったところで食事に行くことになった。取材中のライターさんと原田さんのやりとりを聞いていて、気になる事があったので、ちょうど良い機会なので聞いてみた。
「攻めきれなかったサーキットがあるって言ってたけど、どのコースのこと?」と切り出すと、「ラグナ・セカ」と端的に答えてきた。
「ラグナ・セカか、やっぱりコークスクリュー(名物コーナー)?」 と続けて訊いた。
「コークスクリューに限らず、全体的に攻めきれなかったんだよね」
と、原田さんにしては珍しい答えが返ってきた。
「それちょっと詳しく聞かせてくれない」
と、興味津々に尋ねる。
「長くなるよ。いい?」
と返ってきた。僕にとっては、望むところ。今日は面白い話をつまみに、夕食が食べられるとワクワクしながら何度も頷いた。
「まず何が違うって、ラグナ・セカはヨーロッパのサーキットとリズムが違うんだよね。もちろん日本のサーキットとも全然違うんだ」
と切り出してきた。僕の知る限り、日本のサーキットはアクセルを開けながらクリアするコーナーが少ない。対してヨーロッパのサーキットは、アクセルを開けながら立ち上がるコーナーが多い。というのが僕の見解だった。
「そうなんだよね。ただアメリカのサーキットはまた違って、開けながら立ち上がるにしても開けるタイミングが独特なんだ。そのリズムが掴めないんだよね。パーシャルの時間の使い方って言えばいいのかな。待たないと飛び出すし、待ち過ぎれば遅いし。うまくコース幅が使えなかった印象なんだ」
と、当時を思い出して、表情を曇らせた。
その言葉に対して僕は、「でもそれは1年目の話で、2年目にはわかったんじゃないの」と言った。
「何言ってんの、成績見てよ。2年目の方が悪かったんだよ。もうどこ走っていいのか分からなかったんだよね。特に5コーナーなんて、どこ走っても上手くいかない。砂漠の真ん中だから埃っぽいでしょ、ちょっと間違えるとワイン(ガードナー)みたいに、すぐハイサイドしちゃうんだよね。いろんなラインを試したんだけど、最後まで全くどこを走っていいのか分からなかったよ」
と続けた。その時、僕は「いろんなラインを走った」という言葉に引っかかった。
「ちょっと待って、俺は2年間練習走行から予選、レースと見てきたけどそんなにライン変えてきた?」
「考えられるラインは、時間の許す範囲で全て試したよ。レースなんだから当たり前じゃん」
そう答えてきた。これはグランプリライダーの言う、いつものやつだなとピンときて、質問を続けた。
「ねぇ哲ちゃん、そのラインってどのくらいあるの」
「いや。沢山あるよ」
と原田さん。
「で、どのラインを通してもシックリこなかったんだよね?」
と僕。
「そう、どれも合わなかった」
そう言われたところで核心に触れる質問をしてみた。
「その無数に存在するラインってどのくらいの幅の話? 1m ? いや80㎝くらい?」
と、訳知り顔で質問した。すると。
「そんなに幅なんてないよ。このくらいかな」
そう言って腕を広げて見せた。その幅は、30〜40㎝ほどだった。
今まで何度も話を聞いてきて、GPライダーのマージンや感覚を知っていたつもりだったが、全く話にならない。自分の思う半分以下の幅に無数のラインをイメージし、それでもベストラインを見つけられなかったと言うのだ。たかが30〜40㎝の幅にどれほどラインが存在するのだろう。自分がライディングすれば、それは誤差でしかない数値だ。分かっていたつもりだったが、それは勘違いで、彼らのいる頂ははるかに遠かった。実際に走った違いではなく、ただのイメージですら彼らには遠く及ばなかったのだ。びっくりしない自信があってぶつけた質問なのに、軽く跳ね返され不覚にも驚かされてしまった。
自分がどんな顔をして質問を続けたのか想像もしたくないが、「じゃあその30㎝の中で、ずっと格闘してたんだ」と訊いてみた。「格闘っていうより、迷子になってた感じかな。巨大迷路の中でずっと出口を探して、歩き回ってる感じが近いかな。しかも全くたどり着きそうもなかったな。僕にとっては、本当に厄介なサーキットだったなぁ」
そう懐かしそうに話してくれた。
やはり世界でトップを狙う人間は、桁が違う。たった30㎝の距離に、無数のラインをイメージし、ベストを探す努力をするのだから。しかもそのラインをイメージするだけではなく、限界のスピードを見極め、寸分違わず通していけるのだ。そんな神業みたいなことができる天才でも、時として正解に行き着けないこともあるのだ。
いや、もしかしたら逆に100ラップ以上は重ねたであろうサーキットで、ほんの30㎝の中で迷子になれることこそが天才の証なのかも知れない。