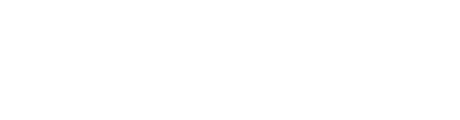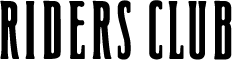パドックから見たコンチネンタルサーカス~日本人初の世界チャンピオン~片山敬済~

’81年から国内外の二輪、四輪レースを撮影し続けている折原弘之が、パドックで実際に見て、聞いたインサイドストーリーをご紹介。今月は、折原自身がバイクレースに惹かれるきっかけになったライダーについて。

あれは僕が中学生だった頃のことだ。何気なくつけたテレビから、日本人ライダーが世界チャンピオンになった番組が流れてきた。そう、’77年の世界GP350㏄クラスチャンピオン、片山敬済選手のドキュメンタリーだ。
最初は「へぇーそんな人がいるんだ」という感じで見ていたが、その頃からバイク好きだった僕は次第に食い入るように画面を見つめていた。当時の僕は、バイクは好きだったがレースにはそれほど興味を持っていなかった。
加えて当時はグランプリの報道などほとんどされていなかったため、片山選手の存在など知るよしもなかった。だから当時の番組で覚えているワードも、“日本人初の世界チャンピオン”、“3気筒のTZ”、“片山敬済という変わった名前”くらいなもの。
ただ、日本人でも世界を相手に、チャンピオンを獲れるんだという事実は確実に深く心に刻まれた。
世界に触れた日
それから3年後、僕は18歳でオートバイ雑誌にアルバイトで潜り込むと、世界は一変した。’81年から全日本ロードレースを取材するため、毎週のようにサーキットに通い始めた。
すると今まで聞こえてこなかったグランプリの情報が、入ってくるようになったのだ。ケニー・ロバーツ、バリー・シーン、コーク・バリントン、といったビックネームに混じって、片山敬済選手の名前もよく聞こえてきた。
「あの時テレビで見たチャンピオンが500㏄クラスで頑張っている。僕も、あのチャンピオンを撮ってみたい」。そんな欲求が大きく膨れ上がっていた。
その後も取材でパドック通いを続けていると、’83年のケニー対フレディの伝説のシーズンが話題となった。自分がその場にいられなかったことを、これほど後悔した事はなかったかもしれない。
そして’83年のワールドチャンピオンとなったフレディ・スペンサーが、全日本ロードレース最終戦の鈴鹿サーキットに来ることが決まった。ついに本物のGPライダーを撮れる。
僕はその日が来るのを一日千秋の思いで待ち続けた。
そして迎えた最終戦はフレディの走りに終始圧倒された。
それまでのコースレコードは大きく更新され、レースでは同年チャンピオンの木下選手がペースについていけず1周目で転倒。追走する平選手ら日本のトップライダーを、たった3周でストレート1本分引き離してしまったのだ。
世界との差を、まざまざと見せつけられた瞬間だった。同時に、こんなバケモノみたいなライダーと、互角にやりあう片山選手を一目見たいという思いが強くなり、何とかグランプリを撮る方法はないものか探し求めた。
そして’84年の冬に、ひょんなことからそのチャンスを掴むことができた。’85年の1月から始まるスーパークロスを撮影するため、後の師匠になる坪内氏の事務所を訪ね、アメリカ取材のアドバイスをもらった。
お礼を言って帰ろうとすると、坪内氏が「今年から『グランプリイラストレイテッド』という本を創刊するから、アメリカから帰ったらうちに来い」と言うのだ。
つまりグランプリが撮れる。ということだ。思いがけ無い申し出に一瞬呆然としたが、躊躇はなかった。二つ返事で話を受け、その年の6月に、渡欧した。
僕にとってのグランプリ初戦はユーゴスラビアのリエカサーキット。当時の拠点であったパリから、1600kmほどの距離だ。
宿泊費を浮かせるため木曜日の夕方に出発し、金曜日の朝まで大谷耕一先輩と交代で車を走らせ、そのまま撮影に入る。ほぼ徹夜で走ってきたのだが、初めてのグランプリ撮影に興奮し、眠気など微塵も感じなかった事を今でも覚えている。
なにせ’78年にテレビで見てから、7年かかって辿り着いた場所なのだ。僕は真っ先に片山選手のピットに向かい、世界を相手に戦う男を撮りに行った。
この時僕には、片山選手の「この仕草を撮りたい」という、はっきりとしたイメージが出来上がっていた。僕のグランプリの最初の一枚は、その写真以外あり得なかったのだ。

金曜日のフリープラクティスが終わった夕刻、片山選手が記者会見を行うというので出席した。その会見とは、片山選手の引退会見だった。
しかも今シーズン一杯とかではなく、パフォーマンスに納得できなくなった時点での引退。という内容だったと記憶している。徹夜で走り一日中撮影して、ボケかかっていた頭をハンマーで殴られたような気分だった。
ある意味、僕にグランプリの魅力をえてくれたライダーが、早ければこのレースで引退してしまう。たった1レースでも間に合ってよかったという思いと、数レースしか撮れないのかと言う落胆。
色々な気持ちが入り混じり、この時の感情はうまく表せないほど混乱した。
その後、引退するまでに、3レースほど撮影する機会に恵まれた。その3レースでは、当時の僕のテクニックがお粗末すぎた。僕が追い求めた一枚は、撮影こそできたものの納得する表現には程遠かった
’78年当時、片山選手はNAVAのヘルメットを被っていた。その頃のNAVAのシールドは、2アクションで開閉する仕組みだった。
1アクション目で上げてあるシールドを下ろし、2アクション目でヘルメットに圧着させるシステムだ。そして下ろしたシールドをホックで止めて、真っ直ぐに正面を見つめる。
ブラウン管から流れてきたこの仕草がやけに印象的で、鮮明に飛び込んできた。そしてこのシーンが僕にとってのグランプリライダーの象徴となった。
シールド越しに見える強い眼差しこそ、僕が真っ先に撮りたかった一枚だ。
’85年のユーゴスラビアグランプリから今日に至るまで、今だにこの瞬間が大好きだ。
僕の中で、ライダーがシールドを下ろす瞬間はスイッチが入る瞬間だ。
速く走ること以外考えない。そんな単純で純粋な眼差しが、中学生だった僕に世界を感じさせてくれた。
その眼差しを追い続けて、今日もサーキットで写真を撮り続けている。