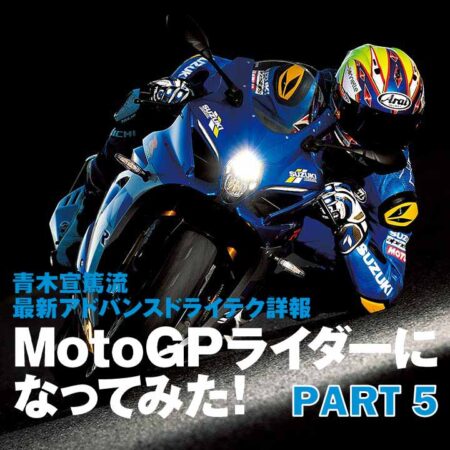【バランスを崩してリーンする。きっかけはプッシングステア】体重移動をしただけでは車体はバンクしていかない

総重心のイン側移動で実バンク角を稼いでいる
直進するバイクのステアリングから両手を離しても、多少は左右に旋回できます。低速なら、両手離しでクルクルと小回りするスタントライダーもいます。このとき使われる力は、体重移動による作用・反作用。つまり、体重移動で絶対に曲がらない、というわけではありません。
しかし、少なくともスポーツライディングでは、俊敏性や応答性、正確性などの理由から、ステアリング入力によるバンク角制御のほうが支配的。それどころか公道でも、皆さん無意識で絶対にプッシングステアしているのですが、低めの速度域だと入力は指先でチョンと触れる程度なので、「ステアリングには入力していない」という感覚になるわけです。

その一方で、MotoGPライダーが、極端なハングオフでイン側に体重移動しているのはなぜなのか? それは、より大きな遠心力とつり合うように重心移動しているからです。
タイヤ接地点と重心を結ぶ線と、重心からの鉛直線が成す角度をバンク角と仮定すると、リーンウィズなら見かけのバンク角と実バンク角は同じ。
対して、ハングオフでライダーの重心をイン側に移動し、車両+人の総重心も車両重心よりイン側に置くと、見かけのバンク角はリーンウィズと同じでも、総重心位置を基準とする実バンク角は深くなっているのです。
(辻井栄一郎)

座る位置で重心の位置は大きく変わってくる



腰をズラすとイン側のステアリングを操作しやすくなる
プッシングステアの基本は、イン側の肘を曲げ気味にして関節をロックし、転舵する方向に肩からステアリングを押す動作。曲げすぎると肘がサスペンションになって力が逃げてしまうが、かといって突っ張ってしまうとまったく操縦できず危険だ。イン側に腰をズラしたフォームは、肘の突っ張りを解消して微調整しやすくなる

トライアルのように低速なら体重移動で操ることは可能
ジャイロモーメントが少ない約30km/h以下で軽量な車体であれば、上半身の体重を大きく移動したり、ステップを踏んだ反作用でライダーの重心を動かして車体を傾けることもできる。
例えばトライアル選手は絶妙な重心コントロールでバランスを取り、スタンディングし続けることができている

ステップ荷重だけでは重心の移動は起こらない
レーシングスタンドのタイヤの下に体重計を置いて左右の重量バランスを計測。片側のステップだけに荷重して腰を浮かせても、身体が車体の中心にあれば、左右の重量バランスは変化しない。左右の合計重量が減っているのは、バランスを取るためステアリングへの荷重が増えたためだ