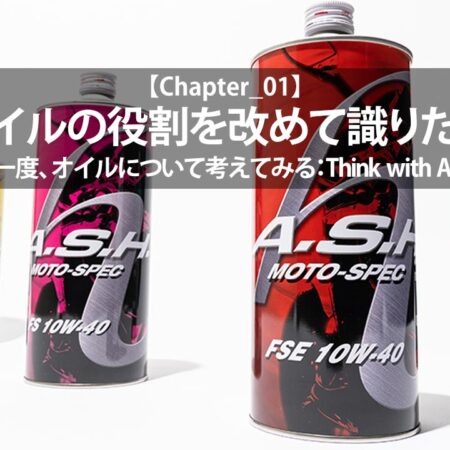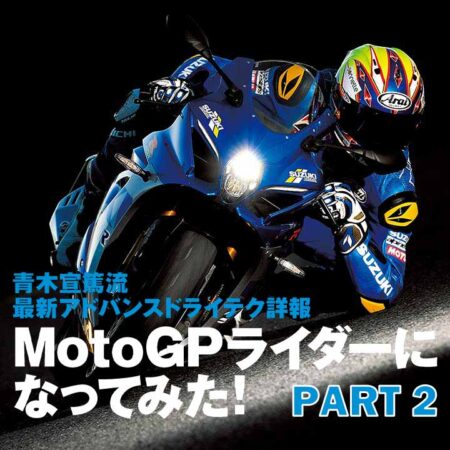YAMAHA MotoGP キーパーソンインタビュー『マッシモ・バルトリーニ』

マッシモ・バルトリーニさんのインタビューは最終戦で行ったものだ。内容が【2024年 YAMAHA MotoGP 変化の起点】と非常にリンクしているので、ぜひともそちらと併せて読んでいただきたい。

ヤマハとドゥカティその違いは?
マッシモ・バルトリーニさんのインタビューは、最終戦ソリダリティGP・オブ・バルセロナの木曜日に設定された。夕方にホスピタリティへ足を運ぶと、すでにバルトリーニさんが待っていて、写真のようなにこやかな笑顔を浮かべていた。「ライダースクラブという日本のバイク雑誌のインタビューなんですが」と説明すれば、「ああ、僕は雑誌がとても好きなんだよ!」とにこにこして言う。
その柔和な様子に、少しばかり面食らってしまった。初対面で人の懐に飛び込んでくる。けれど、嫌な感じは全くしない。それは日本人とは違う気質を持つイタリア人だから、といった理由ではなく、おそらくバルトリーニさん本人が持つキャラクターの魅力なのだろうと感じる。
バルトリーニさんは、過去にはF1チームのフェラーリで働き、そのあと20年ドゥカティにいて、2023年まではビークル・パフォーマンス・エンジニアを務めていた。ビークル・パフォーマンス・エンジニアというのは、ファクトリー、インディペンデントチームを含めた全ドゥカティライダーのための仕事で、シャシー、電子制御、エンジン、タイヤといったパフォーマンスに関わる全てを管理、開発するというものだ。そして、2024年からヤマハ・ファクトリー・レーシングのテクニカル・ディレクターに就任した。
「ヤマハに来ることを決めたのは、非常に挑戦的なことだと思ったからです」と、バルトリーニさんは説明する。「スミ(MS開発部長の鷲見崇宏さん)は『ヨーロッパと日本の企業の働き方をより融合させる』と説明してくれました。日本の企業がこういった試みをするのは初めてのことで、とても興味深いことだと思ったんです」
気になるのは、バルトリーニさんがヤマハという会社をどう感じたのか、ということだ。イタリアの会社で働いてきたイタリア人から見て、日本の企業のやり方はどう映るのだろう、と。
「ポジティブかネガティブかを判断するのはとても難しいです。ヤマハは部品を造るのは遅いですが、ドゥカティよりもはるかに高品質です。一方で、ドゥカティは部品を早く造りますが、品質は少し劣ります。どちらが良い、悪いということではなく、何を必要としているかによるのです」
この答えまでは、想定内だった。ただ、続く回答が興味深い。バルトリーニさんは、焦点を当てるべきは、つまり、問題の原因はそこではない、と考えている。
「現時点で、私にとって本当の違いというのは、レースの世界が『開発プロセスのスピードを加速させる方向』に進んでいることです」
バルトリーニさんは、MotoGPの開発プロセスが加速している、と言うのである。これについては、前項のMotoGP取材会に登場した増田和宏さんにも質問をしたので、ここに増田さんの回答を加えたい。
「2021年にはその加速が始まっていたと思います。他社がやり方を変え、物事の判断や提案のスピードを上げる手法に切り替えていたのに、我々はその変化に気付かなかったのです。当時はまだ我々が勝てていましたから、彼らが着実に差を詰めていたことにも、大きな進化の兆しにも気付きませんでした。
彼らは、開発のやり方を変えたのだと思います。我々は、現在のバイクのファインチューンで翌年のバイクを造る、という考え方でした。しかし彼らは、レーシングバイクの理想、ラップタイムをコンマ1秒でも縮めるために必要なことは何か、という理想側から物事を考えはじめ、そのために何が必要か、という考え方の開発にシフトしていったのでしょう」
現在のMotoGPにおけるドゥカティとヤマハの差は、その蓄積によって生み出されたということだ。
プロセスにおけるスピードアップが必要
2024年、ヤマハもバルトリーニさんの加入による気付きや変化がもたらされ、これまでにないやり方で進んだ。ただ、バルトリーニさんは「さらにプロセスをスピードアップしてほしい」と言い、テストの改善が必要だと考えている。
「テストやライダーからの追加情報が得られない場合には、あるいはライダーの意見を理解しているなら、すでにデータから十分な情報が得られているのなら、決断すべきだと思います。それ以上待つ必要はありません。これがプロセスをスピードアップさせる一つの方法だと思います。
これまで、ヤマハはライダーのコメントを非常に重視してきました。これはバレンティーノ(・ロッシ)の時代から続いているものです。しかし現在のMotoGPは、技術面で非常に高い要求がされています。もちろん、最終的に決断を下すのはバイクに乗るライダー自身ですが、私たちはデータを確認し、分析方法を改善し、ライダーが正しい決断を下せるように手助けをしなければなりません。
また、失敗を恐れる必要はありません。テストをして失敗することも、成功することと同じくらい重要です。もちろん、なぜ失敗したのかを理解できればね。この点において、私たちは改善できると思います」

「目的をもってテストを行うことが大切です」と、バルトリーニさんは強調した。
2024年、ヤマハは多くのプライベートテストを行った。そして、そのテストの仕方が変わり、そこにはバルトリーニさんの哲学があったとも言える。バルトリーニさんはテストの取り組み方について「まだ改善ができる」と考えている。
2025年には、ヤマハが「第2のファクトリーチーム」としてプリマ・プラマック・レーシングを迎え、テストライダーにはカル・クラッチローに加えてアウグスト・フェルナンデスが新たに就任する。プロセスのスピードが上がれば、その効果もより大きなものになる。
敏感になったリアタイヤグリップ改善が課題
それでは、YZR-M1の改善点はどうだろうか。
「全体的に言えば、現時点でバイクのパフォーマンスが劣っている点は、他のバイクと比べてグリップが少し足りないことだと思いますね。私たちのバイクは主にリアタイヤの使い方を改善する必要があると思います。
また、リアタイヤも変化しました。2023年から2024年にかけて、とても敏感なタイヤに変わったのです。ミシュランは2023年から大きく変わっていないと言っていますけどね。よりタイヤを効果的に使えるバイクが、より高いパフォーマンスを発揮する方向に進んでいます。私たちはその点を理解し、同じ方向に進む必要があります」
バルトリーニさんによれば、2024年のリアタイヤは「より高性能になったが、マネジメントが難しくなった」のだという。確かに、シーズン序盤はドゥカティのライダーもリアタイヤに苦しんでいた。しかし、レースを重ねるにつれて適応し、終わってみれば、ドゥカティがシーズンを席巻した。つまり、ドゥカティが2024年のリアタイヤを最もうまく使いこなした、ということになるだろう。

「結局のところ、レースで速く走るためには、タイヤを機能させることが全てです。バイク、エンジン、その他全ての要素は基本的にタイヤをうまく機能させるために存在します。タイヤをうまく機能させることができれば、速く走れるのです。まあ、ストレートは別の話ですけどね。ストレートではエンジンのパワーが必要ですから……。
エアロはタイヤに荷重が加わることで、タイヤがより大きな力を発生させ、コーナーでより速く、より高いスピードで曲がることができます。つまり、すべての要素は最終的にタイヤを機能させるために行き着くのです」
インタビューは20分ほどだったが、話を聞きながら感じたのは、「ヤマハがバルトリーニさんを必要としたのは、彼の人間性もあるのかもしれないな」ということだ。
MotoGPはバイクに乗って争うモータースポーツだが、そのバイクを造るのは人だ。だからこそ、バルトリーニさんという素敵なキャラクターの持ち主の話を聞きながら、2025年のヤマハへの期待感が膨らんでいった。バルトリーニさんというキー・パーソンを迎えた今、ヤマハの前にあるのは上っていく階段だけだ。